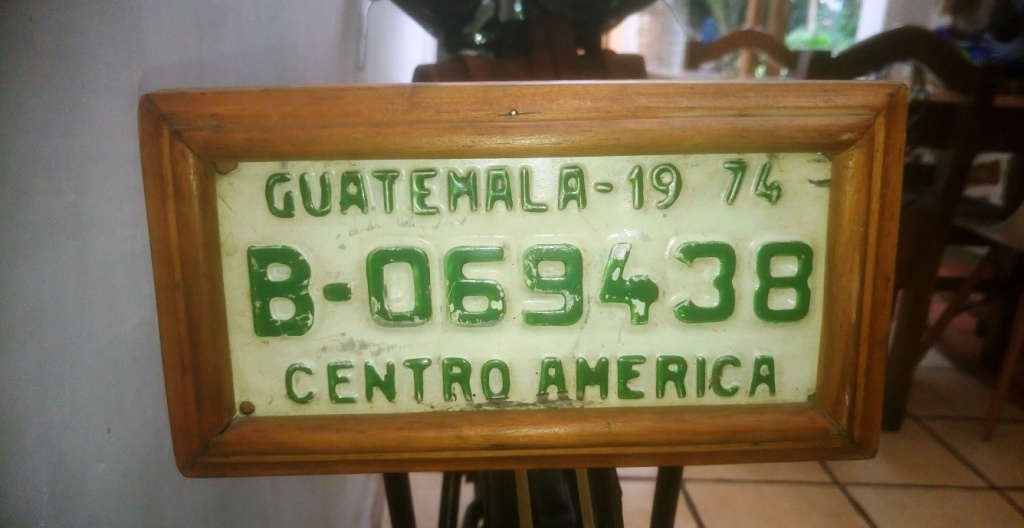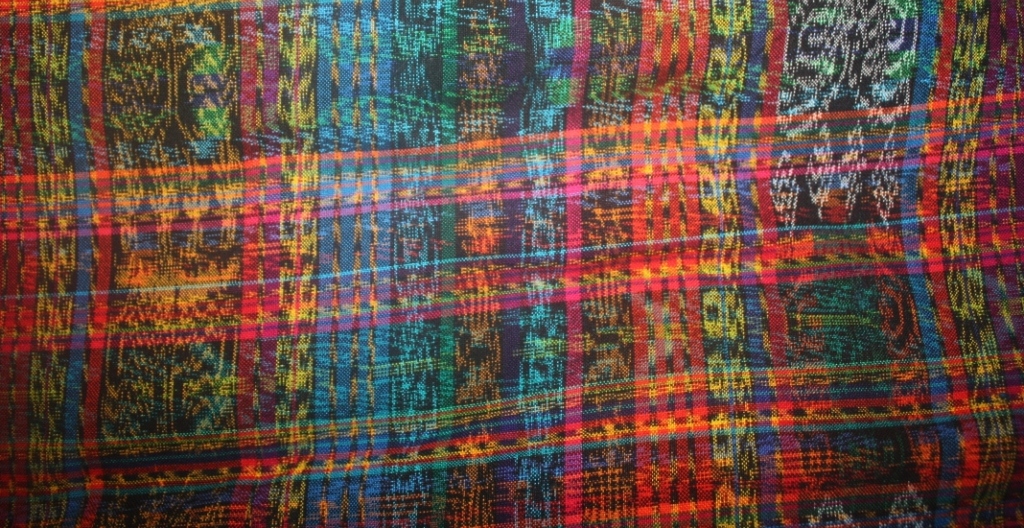今年の学習に関わる宣誓。Manifestではなくoath (juramento)。
Kinya’ ri nuk’aslemal chi uxe’ raqan uq’ab’ ri Qajaw che kipatanixik ri e nuwinaq.
Are taq kinchajij ri rutzil kiwach ri e qanan qatat, ri jun ja winaq, ri jun tinimit; qas kinb’an ri nuchak ruk’ ronojel wanima, ruk’ ronojel nuk’u’x.
Na jumul ta wi kinkoj ri wetamab’al chi ub’anik k’ax pa kiwi’ ri e wajil nutz’aqat.
Kink’xib’ej wib’ kinmej wib’, kinpachab’a’ ri nujolom chi kiwach ri e nab’eal taq winaq, chi kiwach ri saq kiwi’, e k’amal taq b’e, e wajtijab’, ruk’ jun nimalaj maltyoxinik, che qas taqal chi kech.
Kinb’an wachalal chi kech, ke’nuloq’oj konojel ri e wach taq ajchakib’ apawije’ kinriqitaj wi, kwuk’a’j pa ri wanima, xuquje’ nim kwil wi ronojel taq uwach eta’mab’al kik’utum kan chi nuwach.
Ronojel wa’ kinpatanib’ej, kinchakub’ej, mawi kintz’iloj taj, na kwetzelaj taj.
Xane’ kinya’ uchuq’ab’.



 プールは6レーンしかないけど、混雑時を除けばまぁ大丈夫だと思う。
プールは6レーンしかないけど、混雑時を除けばまぁ大丈夫だと思う。